紙と記憶その1「舟を編む」
- Napple

- 2025年7月25日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年9月24日
2025/7/25
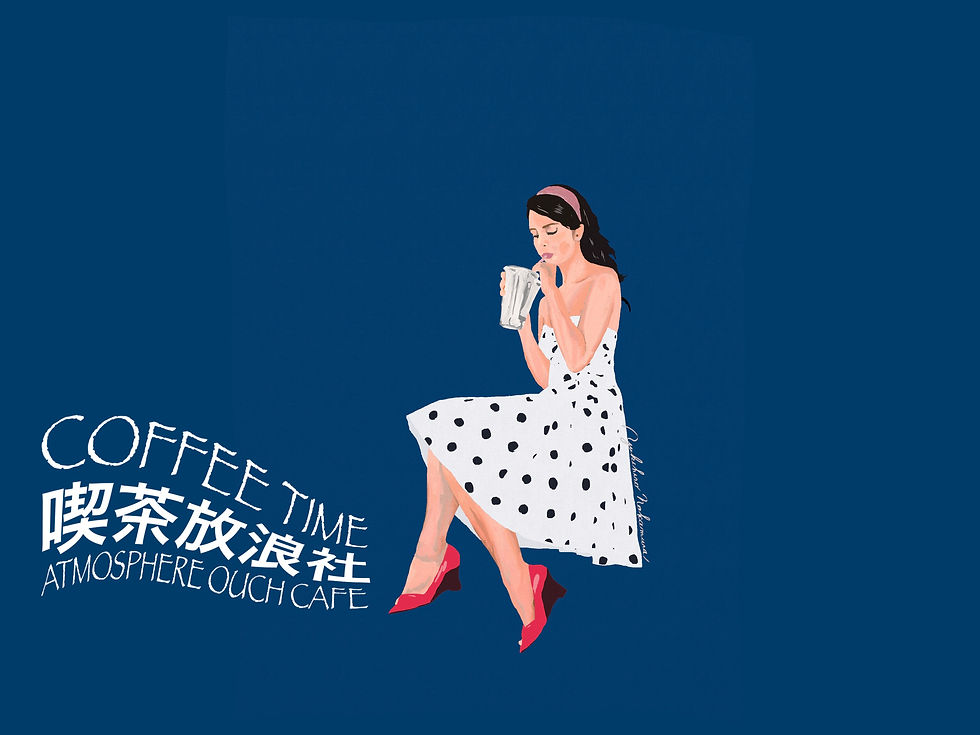
NHKのドラマ「舟を編む」は素敵だ。言葉が愛おしくなる。辞書を引きたくなる。そして、台詞の一つ一つに味わいがある。その第6話では、ついに言葉だけではなく「紙の書物」のあり方にスポットが当たる。私自身そこには未解決の思いがあり、彼らがなんと語るのか興味津々で物語を追った。
経営陣から突きつけられたこと
「より良い辞書を作る上で、紙による制約が枷になっているのではないか。紙はスペースに制限があるから、項目を無限に増やすことはできないし、語釈や用例を最小限に削り込まなければならない。改訂版を出さない限り、情報が古くなっても更新できないし、万が一ミスが見つかっても訂正できない。デジタルにすればそれらの制約がなくなり、より良い辞書作りができる。」
その通りだと思う。
ところが
「枷じゃない、枷なもんか、翼だよ、その制約は辞書をより高みに運ぶ翼だ。」
と、爺さんがいう。確かに「制約のなかで生まれる表現の深み」や、「削ぎ落とすことで立ち上がる余白の美しさ」がある。僕も、紙の書物の素晴らしさ、大切さを感じる者のつもりだ。何より、紙の書物を愛読してきたし、紙の手触りに安らぎを感じる。ではあるが、と同時にデジタルネイチャーでもある。
そして爺さんはぼやく
「時代時代って言ってるけど、必死でついて行ってんだよ、爺さんは!」
ところが、その爺さんが、さらに続けた。
「紙の辞書なんて陳腐化するものの代表かもしれない。でも違うんだよ。紙の辞書に刻み込まれた情報はその時代時代の記録でもあるんだ。価値があるんだよ。・・・いつかきっと全ての辞書から、「男女」や「異性」という文字が消える日が来る。でもね、かつてはあった。恋愛が異性間だけのもだって思われていた時代が確かにあった。その記録を残しておくことはとても大切なことなんだよ。人間がその歴史の中で、いつ何を手放し、何を獲得したのか、紙の辞書にはそのことが詰まってる。」
この言葉には説得力があった。もちろん紙だからできることと言い切ることはできない。しかし、十分に頷ける。確かに、紙に書かれた書物には書き換えることができない情報の持つ確かさ。紙の書物という物理的な存在の持つ確かさがある。それが紙の書物の本質に違いない。
辞書というメディアは単なる「言葉の説明書」である以上に、「時代の鏡」「思想の堆積」であるということでもある。さらにいうならば、辞書は「知の墓標」であり、「進化の航跡」であるとも言えるだろう。時代が変われば言葉も変わる。けれども、その「変わる」ということ自体を記録しておくのは、紙の強さでもある。修正もアップデートもできないからこそ、「そのときどう考えていたか」が、そのまま残る。それは“記録”というより、“記憶”に近いかもしれない。
この回答は次回に持ち越された。そして、紙とデジタル媒体の違いについて思いを馳せていると、僕の思考に全く別の懸念が浮かび上がった。
続く


コメント